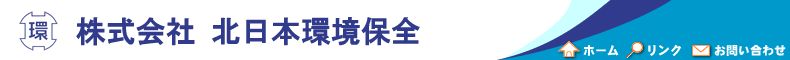
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
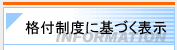 |
||
| 財務情報 | ||
| 産業廃棄物許可内容 | ||
| 産業廃棄物処理実績 | ||
| 二次委託先個社名の公表 | ||
| 組織表 | ||
| 保有資格・人数 | ||
| 講習会受講記録 | ||
| 事業場公開案内 | ||
| 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関情報 | ||
| 産業廃棄物受入処分フロー図 | ||
| 更新履歴 | ||
![]()
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下記のアイコンをクリックするとAdobe社ホームページより、
ソフトをダウンロードできます。
![]()
当社計量証明部門ではCSRの一環と考え、当社の付近を流れる河川、さらに当社が利用する河川として黒沢川と飯豊川の水質を毎月測定しております。 黒沢川・飯豊川採取場所地図
河川水水質データ
水質データの項目について SS(Suspended Solids、浮遊物質量) 水中に浮遊または懸濁している直径1μm〜2mmの粒子状物質のことで、沈降性の少ない粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死骸・分解物・付着する微生物、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿物が含まれる。懸濁物質と呼ばれることもある。 BOD(Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量) 水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量のことで、河川、下水、排水等の有機汚濁を測る代表的な指標。類似の汚濁指標にCODがあり、CODは海域や湖沼で用いられる。 pH(Hydrogen Ion Concentration Index、水素イオン濃度) 水溶液の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標。一般に「水素イオン濃度」といわれ、pHが7のときに中性、7を超えるとアルカリ性、7未満では酸性を示す。 河川水は通常pH6.5〜8.5程度だが、流域の地質、生活排水、工場排水などの人為汚染、夏期における植物プランクトンの光合成等の要因により酸性にもアルカリ性にもシフトする。また、pH5.6以下の雨を酸性雨という。 全りん リン化合物は窒素化合物と同様に、動植物の成長に欠かせない元素であるが、水中の濃度が高くなってくると水域の富栄養化を招くことになる。全リン(総りんともいう)はリン化合物全体のことである。全リンは河川には環境基準値がなく、湖沼・海域に定められている。富栄養化の目安としては、0.02mg/L程度とされている。 全窒素 窒素は動植物の増殖に欠かせない元素だが、水中濃度が高すぎると、富栄養化になりプランクトンの異常増殖の要因となり赤潮等が発生する。全窒素(総窒素ともいう)は窒素化合物全体のことだが、溶存窒素ガス(N2)は含まれない。湖沼、海域には全窒素という指標で環境基準が設定されているが、河川にはない。富栄養と貧栄養の限界値は0.15〜0.20mg/L程度とされている。
|
|||
| Copyright (C) kitanihonkankyohozen All Rights Reserved. |
| 株式会社 北日本環境保全 岩手県北上市常盤台四丁目11番116号 TEL 0197-65-3166 / FAX 0197-64-5533 / E-mail info@kitakan.jp |
